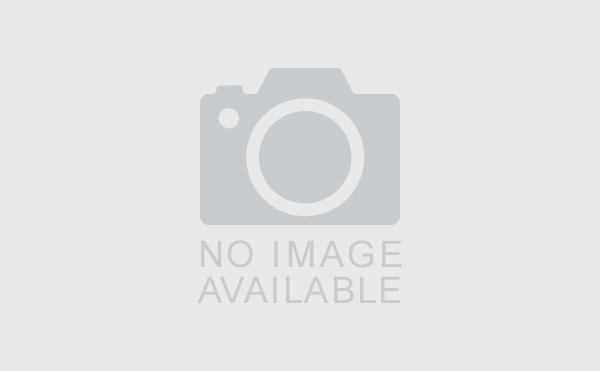結局、説きふせられて――ローラ・ピアニ『ジェーン・オースティンが私の人生をダメにした』
実は、今シーズンもっとも楽しみにしていたローラ・ピアニ『ジェーン・オースティンが私の人生をダメにした Jane Austen a gâché ma vie』は、期待とは少し異なる作品だった。
予告編から明らかに低予算であり、『ジェーン・オースティンの読書会』というよりも『静かなふたり』のような佳作であることは予想していたのけれど、それにしてもストーリーが少し腑に落ちないままだ。もっとも、上映中には「耐えられないわ!」と大きな声で喚きながら退席した中年夫婦もいたのだけれど、そこまでの酷さは感じない。とはいえ、傑作とは手放しに言えないモヤモヤ感が残る一作だ。
*
両親を亡くして以来、妹とその子供と暮らすアガタ・ロバンソンは、文学少女がそのまま大人になったような女性だ。彼女はシェイクスピア・アンド・カンパニーで働いていて、お薦めを聞かれればいつでも「ジェーン・オースティンの『高慢と偏見』」と答える。友だちは少なく、家族以外の話し相手は同僚の男性フェリックスぐらい。自らを『説得』のアン・エリオットにたとえる彼女は性愛を避けていて、「都市化された性」とセックスを少し小馬鹿にしている頭でっかちな一面もある。
実は、アガタには作家になるという夢があり、小説をたびたび書いてみるのだが、いつもどうしても結末まで辿りつくことはできないままだ。ある日、ジェーン・オースティン・エージェンシーという団体に、そんな彼女の書きかけの原稿をフェリックスが勝手に送ってしまう。すると数日後にエージェンシーから返信があり、才能ある作家とみなされたアガタはエージェンシーに招待され、オースティンの遺した屋敷で原稿に集中するスタージュの権利を得ることになる。
言い合いばかりだったけれども何だかんだで仲良しなフェリックスから送り出される際にはキスをされることで、ついに物語が加速する。イギリスの地を踏めば、オースティンの子孫だというオリヴァーが待ちかまえていて、彼ともなんだかんだでいい感じになる。オースティンの子孫のくせに「ディケンズの方が凄い」と突っかかってくるオリヴァーに、「これまでの男性作家たちが女性を怪物のように描いてきたのとはちがって、ジェーン・オースティンこそが人間としての女性を描けるようにした」と言い返すアガタの姿を見れば、恋仲になることは容易に想像がつくだろう――《男性が男性のことを物語にするんですから、女性よりも有利に決まっています。これまで男性のほうが教育レベルも高くて、ペンを執ってきたのも男性なのですからね》。《私たち、お互いに、ちょっとばかり自分の性別に偏った見方をして、それに乗っかって、自分の側に都合のいい例を、自分の知っている範囲から引いてきて組み立てようとしているのですもの》(『説得』)。
結局、アガタは「オースティン的女性」――夢見がちで、早とちりで、好きな人にこそ対抗心を剥き出しにしてしまう人物なのだ。そして、物語は「フェリックスとオリヴァーの二人からどっちを選ぶのか」という王道ラブコメの展開になっていく。
*
どうやらジェーン・オースティン・エージェンシーは架空の団体だそうで、現実には存在しないらしい。そんな架空の団体と建物を舞台に、牧歌的なイギリスの田園風景を描くのは悪くはないのだけれど、リンゴを積んだトラックの荷台に乗って移動する男女のシーンなど、「悪くはないけどすごく心に響くわけでもない」というシーンが大半を占めている。ただ、どのシーンも『エマ』や『マンスフィールド・パーク』で描かれた田舎の風景を彷彿させるし(『ノーサンガー・アビー』ではないかな)、オースティンファンも監督の解釈違いを責め立てたりはしないと思う。
ちなみに、シェイクスピア・アンド・カンパニーはパリのノートルダム大聖堂の前に実在する書店だ。ここは、パリでもっとも有名で歴史ある英語書籍の専門店なのだが、最近はむしろ映えスポットとして有名だ。店舗の前では、大量の観光客が四六時中ポーズを決めて写真を撮っているために、残念ながら劇中の風景とはまったく異なっている。
とにかく、言及しようと思えるほど印象に残った画面は少ないが、文学の引用(デュラスやウルフ、クララ・ツェトキンが言及される)もわざとらしくはないし、初監督作品とは思えぬほど落ち着いた作品全体の雰囲気は評価に値すると思う。
*
それでも腑に落ちないのは、冒頭、セックスをあれほど批判していたアガタが、フェリックスのキスを受け入れたり、オリヴァーと盛り上がってセックスをしようとすることだ。無論、アガタは性愛に奥手で虚勢を張っていただけで、リードしてくれる男性を待っていた可能性もなくはない。そうした物語としては、ストーリーの論理に破綻が生じているわけではないし、何ら批判する点はないのだが、それでも個人的には、「結局、最後はセックスなのか」と言いたくなってしまう。
たしかに、オースティンの小説は、恋愛経験が浅く勘違いしがちな主人公が、最後は良き恋人を見つける話が大半だとしても、21世紀の現代には、それだけではない彼女の作品の一面を見出して、映画の展開に利用してほしかった。とりわけ本作は、女性作家の評価や社会における女性が置かれた状況についての批判的な台詞を多く含んでいるのだから、性愛のかたちについても男女の性器結合が最終目的なものとは別のかたちを見せてくれてもよかったはずだ。
たとえば、2023年に出版された『情熱とけりをつけるために Pour en finir avec la passion』という優れた批評書では、『説得』について次のように言及されているのだが、こうした指摘を採用してもよかったのではないか。
アン・エリオットの不信感は彼女の性格だけではなく、客観的な事実によっても明らかであることを今一度指摘しておこう。彼女は献身的な行為を恐れ、どんな男性も信じない行き遅れの女というわけではない。男性が誠実にひとを愛することができると考えており、男女間の争いをしたいわけではない。『説得』はロマンチックな愛が存在しないと言いたいのではなくて、たとえ周りの人が信用していようとも、どんな人も盲目的に信用するのはいけないということを伝えているのだ。[…]ジェーン・オースティンの小説の強みとは、もはやうぶではなく、自分の運命を決めるために自らの経験を生かせる若い女性を描いていることである。
そして、シェイクスピア・アンド・カンパニーが舞台なら、シルヴィア・ビーチとアドリエンヌ・モニエを扱ってほしかった。20世紀の前衛文学の流布に尽力したこの二人の女性の関係に言及したほうが、本作の性愛への解釈は一段上にいったのではないか。色々と物足りなさを述べたものの、日本でも公開されて、色々なひとの感想を聞いてみたい作品だ。